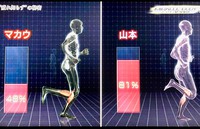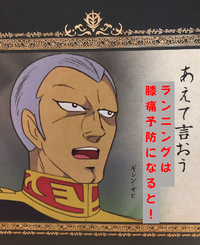★参加者募集★【ミニトランス・ジャパン・アルプス・レース事務連絡】 ←ここクリック
★参加者募集★【ミニトランスジャパンアルプスレース!畑薙ダムから大浜海岸まで】 ←ここクリック
みんな読んでね♫♫【静トレ宣言】 ←ここクリック
2019年08月03日
【相馬剛に教えてもらった】後編
つい最近です。相馬剛さんに教えてもらった走り方が分かったのは。
完全に理解し、解明できた


不思議な感覚です。
間違いなくこれだ
 と言う断固たる確信があります。
と言う断固たる確信があります。それは、わたくしの走り方が上手いという意味ではありません。
走りの理屈が分かったという意味です。
ランニングフォームに対する今までの様々な疑問が解決し、人体構造上の理屈にも合っているのです。
5年以上かかってしまいました。答えに辿り着くのに。
それまでもフォーム改造は、かなり出来ていました。たぶん80%以上は出来ていたと思います。
でも一方で「何かが確かに足りない」という事も確かに分かっていました。
一つは、腕振りの質量問題です。脚と腕の質量バランスが取れていないのです。
もう一つは、再現性の問題です。ある程度の速さで走るとフォームが良くなって、まとまってくるのですが、1㎞5分以下のペースになるとフォームが乱れやすいのです。
これは人類進化と矛盾します。
人類は、もともと1㎞5分くらいのペースで走るように進化しているはずです。
アフリカの草原を、裸足で走って持久的狩猟を行っていた人類は、それほど速く走れないのです。気温は高いし、地面は不安定だし。
せいぜい1㎞5分くらいかそれ以下のペースです。わたしたちは、アスファルトの上をシューズを履いているので速く走れるだけです。
人類はそのくらいの速さで走るのに適した進化をしているはずです。
だから、1km5分以下で走ってフォームが乱れるというのは、理屈に合わないのです。
何かが足りない。
最後の答えが分からないまま、それでもフォーム改造は80%以上は出来ています。
確かに結果は出ました。
フルマラソンのベストタイムを10分更新。
トレラン大会でも、地方のローカル大会ですが、年代別の表彰台に立つことが出来ました。
あれだけ苦手な登りでも引離されなくなりました。
そして何より嬉しいのは、現在に至るまでケガを全くしなくなりました。
鵞足炎も、あの足底腱膜炎も。
今現在、膝のストレッチも足裏のストレッチも一切やっていません。足裏を揉むのもやめました。
足の指の体操やタオルギャザーも一切やめました。
それでもわたくしの足底腱膜は、全く痛む事が無くなりました。
2016年、2017年、2019年ONTKE100(ウルトラトレイル大会)を走っても、足裏は全く違和感なく、触っても一切痛くありませんでした。
【フォームを変えるのは苦痛でしかない】
ランナーなら誰でもフォームを気にしたことがあると思います。
フォーム改善に取組んだことがあると思います。
しかし「フォームを変える」と言っても実際には部分的に多少変えていることが殆どです。
ちょっと変えているだけです。
それは「フォーム修正」、「フォーム微調整」と表現した方が正しいと思います。
フォームを変えてパフォーマンスをアップさせるという事は、全部を変えるという事ではないかと思います。
いわば「フォーム改造」だと思います。

「BORN TO RUN」という本の一節です。
この本は有名なランニング本であり、ベアフットランニング、ワラーチブームを巻き起こしました。
ケガに悩まされていたこの本の著者が、フォーム改造に取組み、その大変さを記述しています。
今までの人生で一度もやったことが無い動きをやるのです。
簡単に出来るはずがありません。
それは技術的な問題だけではありません。
筋肉そのものも今までと異なる使い方をしなければなりません。
地面から伝わる感覚も変わります。
フォーム改造に取組んで「走りやすい」なんて感覚には絶対にならないのです。
苦痛と違和感でしかありません。
体がギクシャクして走りづらい。
脳も体も新しいフォームを全否定してきます。
それでもそれに抗ってフォーム改造を続けるのです。嫌になります。
だからほぼすべてのランナーが「フォーム微調整」だけになってしまうのです。
フォアフット走法にチャレンジしても、足裏の着地場所だけ変えて、簡単にフォアフット走法(トレイル走法)を身に付けようとするのです。
「走りやすい」事と「パフォーマンス向上」は全くイコールにはならないと思います。
それは単に自分が動かしやすいように動かして「走りやすい」と感じているだけで、他のランニングフォームを知らないから比較できないだけです。
「走りにくいフォーム」イコール「悪いフォーム」と安易に判断して、いとも簡単にフォーム改造を諦めるのです。
今まで身に沁みついてきたランニングフォームを全部捨てて、全く新しいランニングフォームに作り替える。
そんな経験をしたランナーは、ほぼいないと言っていいと思います。
ここで言いたいのは、ランナー批判ではありません。
あなたがフォームを変えようと思ってチャレンジして「走りにくい」と思ったら、「正解かも」という事です(体の負担が増えてケガするフォームは間違いです)。
3か月間は、まともに走れないかもしれません。でもそれで「正解かも」です。
今までの自分を変えるのです。それくらいの時間がかかって当然です。
【相馬剛の走り方は正しい】
なんでわたくしが、ランニングに関する事を、出来るだけ人体構造に基づいて、細かく説明しているのか。
それは相馬剛の走り方が、教えてくれたことが、間違いなく正しいという事を証明したいのです。
この走り方は、「日本のランニングの常識」とはほとんど異なる走り方です。
何の実績もない一市民ランナーであるわたくしが、何か言ったところで何の説得力にもならないです。
だから運動生理学、スポーツバイオメカニクス、機能解剖学を学びました。
「人は、走る為に進化している」
そして人の体は、純粋なまでに「ランナー」です。
だからランニングに関する様々な疑問の答えは、「体」が知っています。
本当に正しい走り方は、体の構造と一致しているはずです。真実は、体が知っています。
そうでなければ辻褄が合いません。
私たちの知る日本のランニングの常識は、体の非常識かもしれません。

写真が残ってた♫♫ネット上の他人様の写真を無断転載しています。
今ならよく分かります。
あの日、あなたが、なんで私に走り方を教えてくれたのかを。
あなたが、なんであのような教え方をしたのかを。
あなたが教えてくれた事の本当の意味を。
すべてはトレイルを安全に走る為。
これはトレランを安全に楽しむためのテクニック。
今までのランニングに関する様々な疑問が一気に解決しました。
あなたに教えてもらった走り方が分かって、今はまた練習が楽しくてしかたないです。
トレイルで試したり、登りで試したり・・・・・・色々試して、工夫して・・・・・・・。
あの日、見えなくなったあなたの後ろ姿が、少し見えた気がして、とてもトレイルランニングが楽しいです。

【ランニングと膝】SSC機能その①
【ランニングと膝】膝のランニング機能その②
【ランニングと膝】膝のランニング機能その①
【ランニングと膝】膝の構造についてその②
【ランニングと膝】膝の構造についてその①
【相馬剛に教えてもらった】中編
【ランニングと膝】膝のランニング機能その②
【ランニングと膝】膝のランニング機能その①
【ランニングと膝】膝の構造についてその②
【ランニングと膝】膝の構造についてその①
【相馬剛に教えてもらった】中編
Posted by 静岡トレイル・ランニング・サークル(静トレ) at 09:14│Comments(0)
│静トレマガジン