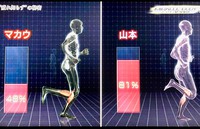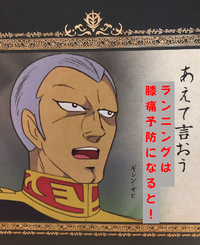★参加者募集★【ミニトランス・ジャパン・アルプス・レース事務連絡】 ←ここクリック
★参加者募集★【ミニトランスジャパンアルプスレース!畑薙ダムから大浜海岸まで】 ←ここクリック
みんな読んでね♫♫【静トレ宣言】 ←ここクリック
2019年10月21日
【ランニングと膝】SSC機能その①
【膝のバネを使って走る】
前回のブログで登場したSSC(ストレッチ・ショートニング・サイクル)機能について観ていきます。
SSC機能は、主に腱組織で発揮されます。
腱と言えば、アキレス腱です。
フクラハギの筋肉の下の白くなっている所が腱組織になります。
アキレス腱は、腓腹筋とヒラメ筋の二つの筋肉と繋がっています。
人体最大の腱組織と言われます。
しかし実は膝関節周辺にも沢山の腱組織があります。
まず腸脛靭帯です。
上の画像でスネの骨と繋がる白くなっている所が腱部分になります。
断面積、長さ共に大きな腱組織でアキレス腱に匹敵し、大殿筋と言う極めて強い筋肉と繋がっています。強靭な腱組織になります。

そして鵞足に繋がる縫工筋(ほうこうきん)、薄筋(はっきん)、半腱様筋(はんけんようきん)です。
特に半腱様筋は、名前の通り「半分が腱の様な筋肉」で、腱組織がかなり発達しています。
しかもハムストリングの一つでもあるので筋肉も大きく強い力を発生させ、SSC機能も強く発揮できます。
鵞足の腱組織は、三つに分かれていますが、三つを合わせれば腸脛靭帯と並ぶ強靭な腱組織になります。
このように膝にも、強力な腱組織があり、それらを合計した断面積はアキレス腱を十分に上回ります。
SSC機能は、ランニングの能力(ランニングエコノミー)の重要な要素です。
しかし、ブログでも書いた通り、SSC機能の発揮には個人差が大きく(ジャンプ貢献度0%~73%)、ジャンプ動作でSSC機能を全く使えていない人もいれば、十分に使いこなしている人もいます。
これはSSC機能の持っている構造的な特徴によるものです。
この特徴を知らないといつまで経っても身に付ける事が出来ません。
特徴①
「SSC機能は、伸ばされないと発揮できない」
SSC機能は、筋肉と腱組織が協力して発揮する能力です。
これを筋腱複合体と言います。
筋膜と腱組織は、二種類の繊維組織(弾性繊維と非弾性繊維)が網状に交差した構造をしていて、通常それが波のように折りたたまれた状態になっています。

弾性繊維と網目と波状の構造により、筋腱複合体はバネと全く同じ機能を発揮します。
バネと同じですので伸ばされなければ、一切機能を発揮出来ません。
私達がジャンプする際にも、一度かがんだ方が遠くへジャンプできるのは、筋力だけでなく腱も伸ばされて力が蓄えられるからです。
特徴②
「タイミングが大事」
SSC機能は、瞬間的に伸ばされて、瞬間的に縮まる事で発揮されます。
ジャンプ動作の実験では、ジャンプのタイミングを僅かに遅らせただけで、SSC機能が低下し、ジャンプ力が減る事が分かっています。
着地後、時間にして0.03~0.07秒のタイミングになります(ケニア人の着地動作から推計)。
私達の感覚的には、ほぼ同時の感覚です。
着地の瞬間に発生する力なので、「蹴って走る」、「着地後に重心移動させる」ような感覚では、SSC機能は殆ど使えていないことになります。
特徴③
「意識して使えない」
SSC機能は、腱組織の動きが重要になりますが、この腱組織は脳の神経支配(遠心性神経支配)を受けてなく、意識して使う事が出来ません。
腱組織を意識して力を込めても全く反応しません。
その為、SSC機能を発揮させるには、着地の前に体の動きをそうなるように誘導する必要があります。
つまり着地の仕方によって決まります。
ジャンプ力は着地の仕方によって増すわけです。
着地してから力を込めて蹴っても遅いのです。
ジャンプの練習よりも着地の練習の方が重要になります。
特徴④
「予備緊張が必要」
予備緊張とは、体が動く前(着地する前)に筋肉が活動を始めている状態の事を指します。
SSC機能は、筋肉は伸びず、腱組織だけが伸ばされた時に発揮します。
そして腱組織が縮む時に、タイミングよく筋肉も縮むと効果を発揮します。
着地衝撃で腱組織と共に筋肉も伸びてしまうとSSCの効果は、大きく減ってしまう事が実験によって確認されています。
筋肉が伸びてしまうとその分腱組織の伸びが足りず、筋肉の縮むタイミングも遅れてしまいます。
着地の際に筋肉を伸ばさずに、腱組織だけを伸ばすには、筋肉をあらかじめ緊張させる必要があります。
これが予備緊張です。
単に着地して関節を曲げるだけでは、SSC機能は発揮されません。
予備緊張がある事で、筋肉はタイミング良く力を発揮させることができます。
ランニングで言えば、着地する直前0.03~0.06秒前にフクラハギやハムストリングなどが、活動を始め緊張している状態になります。
しかし、この予備緊張は意識して行うことが難しく、殆ど無意識(感覚的)に行われます。
着地前の体の動かし方や日頃の練習で感覚的に身に付ける必要があります。
着地の練習を繰り返すことによって神経系機能が改善され、予備緊張を的確に発生させることが出来るようになります。
マカウ選手が、着地前に「振り戻し動作」をしている事を書きましたが、あの動きが脚に予備緊張を発生させる動きになります。
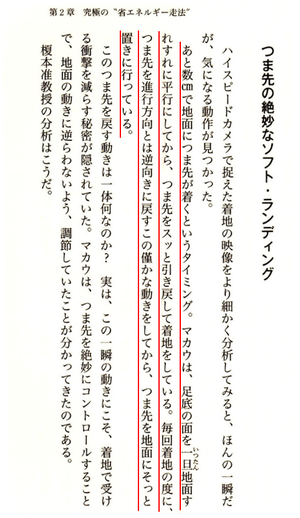

振り下ろし動作は、後ろから前に持ってきた脚を止めて、かつ後ろに引き戻す(振り戻す)動きになるので、大殿筋、ハムストリング、フクラハギの筋肉を使います。
振り下ろし動作の時に予備緊張が発生します。
振り下ろし動作を身に付ければ、SSC機能も同時に身に付ける事になります。
つまり着地の練習は、予備緊張の練習であり、SSCの練習であり、ジャンプ力の練習であり、フォアフット走法の練習になります。
それぞれを分けて考える必要は無く、最初の動きさえ間違わなければ一連の動きとして体が自然と反応してくれます(バイオメカニクス的な力が発生する為)。
人間の体がそのように進化しています。
ランニングに於いては、着地直前の動きと着地の練習が最も重要になります。
着地が上手くできれば、自然とジャンプ力は増します。
ランニングの基本であり、大事なのは「着地の練習」になります。
特徴⑤
「柔らかすぎる筋肉と腱ではSSCは発揮されない」
筋肉と腱組織が柔軟性があって柔らかいとSSC機能は低下する事が、いくつもの実験で明らかになっています。
体は柔らかい方が良い。筋肉と腱組織は、柔らかく伸びた方が良いと従来言われてきました。
しかし実験で、静的ストレッチはケガ予防効果が無い事が分かっています。
静的ストレッチとは、アキレス腱を伸ばしたり、開脚や前屈などの柔軟体操です。
さらに静的ストレッチは、疲労回復効果が乏しいことが分かっています。
柔軟体操と疲労回復はあまり関係が無いようです。
そして静的ストレッチによって、筋腱複合体の弾力性が低下してSSC機能が低下することも分かっています。
SSC機能だけで無く運動パフォーマンスが低下します。
また、開脚や前屈で体がべったり付くような人は、腰痛になりやすい傾向があるそうです。
これはハイパーモビリティによって関節異常になってしまうからです。
筋腱複合体は、適度に硬い(弾力性のある)方が機能を発揮します。
また筋肉が温まっている方がいいようです。
ですので動的ストレッチが、準備運動には最適なようです。
【注意】
筋肉と腱は硬い方が良い、と言う意味ではありません。。
機能的で弾力性がある方が良いという事です。
過度な柔軟性も過度な硬さも、体をおかしくしてしまいます。
また、ここで述べている「柔軟性」は、筋肉を伸ばしたりする時の柔軟性です。
筋肉を「触った時の柔軟性」ではありません。
筋肉を触った時に硬いのは、過緊張や疲労状態であり、最適な状態ではありません(肩こりがその一例)。
特徴⑥
「筋肉の負担が減る」
実験では、SSC機能を発揮できると、ジャンプ力が増すのに、筋出力が減ることが分かっています。
ランニングで言えば、速いのに、軽く走れるという感覚になります。これは凄い。
長距離走では、ゴリゴリの太い筋肉の脚は、重くて不利になります。
SSC機能を利用できれば、脚は自然と細くなります。
ですのでランナーで、脚が太くなったという人がいますが、間違いなく走り方の問題と言えます。
特徴⑦
「腱組織は、疲労しにくい。エネルギーも酸素も使わない」
腱組織によるジャンプ力は、機械的なものなので、筋肉に比べ遙かに疲労しにくいです。
しかもエネルギーも酸素もそれほど必要としないので、持久走では圧倒的に有利になります。
腱組織の耐久性(走れる距離)は、練習で伸ばせますので、日頃の練習が重要です。
特徴⑧
「SSC機能は、練習で向上する」
SSC機能は、人間本来の機能なので誰でも出来ます。
そしてSSC機能は、練習度合いによって向上します。
ですので、あきらめず地道に基本練習をやれば出来ます。
特徴⑨
「SSC機能を使うつもりで練習しないと身に付かない」
実験結果では、単にジャンプの練習をしただけでは、筋力でジャンプするようになってしまいSSC機能が身に付かなかったケースもあるそうです。
現代人は、裸足の習慣が無く、裸足で走ることも無い為、SSC機能を使ったことが余りありません。その感覚もありません。
その為、筋力でジャンプしたり、筋力で走る癖が付いているので、何も考えずにただジャンプしてもSSC動作は、身に付きません。
筋力を使わずに、タイミングよく跳ねる意識を持って練習する必要があります。
蹴らずに走る感覚が必要になります。
特徴⑩
「SSC機能を実感するには時間が掛かる」
腱組織は、筋肉に比べ成長が遅い為、ランニングでの効果を実感するのに最低でも1か月はかかります。
また着地前の動作でSSC機能の発揮が決まるので、動作練習も必要になります。
練習回数が少なければ、もちろんその分、腱組織の成長は遅れ、動作も身に付きません。
ですので、いきなりやっても実感できないことも多いと思います。
気長に地道に基本動作の練習が必要になります。
【ランニングと膝】膝のランニング機能その②
【ランニングと膝】膝のランニング機能その①
【ランニングと膝】膝の構造についてその②
【ランニングと膝】膝の構造についてその①
【相馬剛に教えてもらった】後編
【相馬剛に教えてもらった】中編
【ランニングと膝】膝のランニング機能その①
【ランニングと膝】膝の構造についてその②
【ランニングと膝】膝の構造についてその①
【相馬剛に教えてもらった】後編
【相馬剛に教えてもらった】中編
Posted by 静岡トレイル・ランニング・サークル(静トレ) at 21:24│Comments(2)
│静トレマガジン
この記事へのコメント
とても分かりやすく参考になりました。
感覚的に走っていたのが、これを読ませていただいて意識して練習に取り組めそうです。
でも予備緊張は意識的には難しいとか感覚の大切さも再認識させられた良記事でした。
感覚的に走っていたのが、これを読ませていただいて意識して練習に取り組めそうです。
でも予備緊張は意識的には難しいとか感覚の大切さも再認識させられた良記事でした。
Posted by はだしの人 at 2019年10月30日 12:16
コメントありがとうございましす。
そうなんですよ。
体の構造を理解した上で走ると、ランニングフォームにも迷いもなくなりますし、
フォームが乱れても、自覚してすぐに直せるんですよね。
まだまだ書いてないことがあります。
役に立ってわかりやすく、でもハイレベルな記事を目指します。
そうなんですよ。
体の構造を理解した上で走ると、ランニングフォームにも迷いもなくなりますし、
フォームが乱れても、自覚してすぐに直せるんですよね。
まだまだ書いてないことがあります。
役に立ってわかりやすく、でもハイレベルな記事を目指します。
Posted by 静トレ at 2019年10月30日 22:05